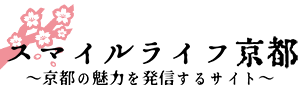夏の京都

祇園祭には多くの見物客が集まる
京都の夏を代表するものといえばやはり祇園祭でしょう。
八坂神社で行われる祭礼であり、毎年7月1日から1ヶ月間行われる京都の夏の風物詩です。
そのため、全国各地から多くの見物客が集まり、とても盛り上がります。
千年以上もの歴史を誇る祭りであり、昔ながらの文化が現代にまで残されているのです。
元々は疾病退散を目的としたものであり、当時の平安京で疾病が大流行して人々の恐怖を取り除くために祇園祭が始まりました。
祭りとしての歴史や規模は世界でも有数であり、日本を代表する祭りといえるでしょう。
日本人の精神性に大きな影響を与えてきた祭りであり、長い歴史を感じさせます。
応仁の乱が起きていた時や第二次世界大戦中には一時的に中断されていましたが、それ以外の時期ではずっと祇園祭が毎年行われてきました。
中でも7月14日から17日が最も人の集まる時期です。
祇園祭の見どころとしては、まず17日の午前9時から始まる前祭山鉾巡行があります。
これは2時間をかけて市の中心部を巡行します。
24日には還幸祭が行われるのですが、こちらも多くの人が集まり熱気に溢れます。
日本語の表現としてあとのまつりという言葉がありますが、これは祇園祭から生まれました。
祇園祭の山鉾巡行はかつては17日と24日に分けて行われており、後者をあとのまつりと呼んでいました。
そして、あとのまつりの方は既に17日に比べると地味なために、24日に行っても既に盛り上がりは過ぎており、ここからあとのまつりという表現が誕生しました。
大文字五山送り火とは
祇園祭の他にももう1つ京都の夏を代表するイベントがありそれが大文字五山送り火です。
毎年8月16日になると大文字山でかがり火が行われます。
これは大文字の送り火と呼ばれることが多いです。
全部で5つの山で順番に点火されていくため、大文字五山送り火と呼ばれることもあります。
これによって死者の霊を無事にあの世へと送り届けることができます。
京都の夏の夜を彩る伝統行事であり、夜の8時頃に点火が始まります。
起源については明確なことは分かっていないのですが、平安時代や江戸時代からだという説があります。
具体的な史料として出てくるのは近世になってからです。
京都の地元の人の中には大文字焼きという呼び方を嫌っている方もいるため気をつけましょう。
他では見られない貴重な光景を目にすることができるため、価値があります。
とても大規模なものであり、生で見るととても迫力があり、その光景は忘れられないでしょう。
単に宗教的な行事としてだけではなく、観光資源としてもとても貴重です。
民間で数百年もの間受け継がれてきた伝統であり、これからも存続するでしょう。