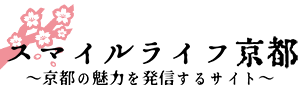京都弁

うつくしい響き
京都には独特の方言が根付いており、京都弁や京ことばといわれることが多いです。
関西地方というのは関西弁としてひとくくりにされることが多いのですが、実際はそれぞれの地域で話されている言葉に違いがあります。
その中でも京都弁は独特のものとなっているのです。
あまり京都弁という呼ばれ方を京都の人達は好んでおらず、京ことばと呼んだ方が喜ばれるでしょう。
たとえば、行かないや来ないを京都では行かへんやきーひんといいます。
ちなみに大阪弁では、行けへんやきやへんという風に話します。
京都弁として有名なものにそうどすがあり、これは女性言葉のように思われていますが、昭和のはじめ頃までは男性が使っていました。
おおきには京都で使われていることが多いのですが、これにはありがとうという意味だけではなく、こんにちわやさよならなどの意味でも使われます。
京都弁は年配の方ならば普通に使っているのですが、若い方のほとんどは本来の京都弁ではなく、一般的な関西弁を使っているケースが増えています。
ひとくちに京都弁といっても、商人や舞妓、職人、農村部の人達などそれぞれ使っている言葉は違いました。
しかし、テレビでは舞妓さんの使っている言葉が注目されることが多いためにそれだけが京都弁だと思われています。
京都はみんなどすと語尾につけて話していると思っている方は多いかもしれませんが、実際にはほんの一部の方のみです。
関西に住んでいる人でないと京都弁と関西弁を見分けることは難しいでしょう。
京都弁の例
たとえば、京都では北に行くことをあがるといい、南に行くことをさがるといいます。
かつては御所に行くことをあがると表現されていました。
いけずという表現がありますが、これは意地悪をする人のことです。
いぬは往ぬあるいは去ぬと書き、立ち去るや帰るという意味です。
女性は自分のことをうちと言うことがあり、これは他の地域でも使われています。
ようこそいらっしゃいましたという意味でおいでやすやおこしやすという表現があります。
くすぐったいという意味でこそばいといいます。
あくどいや辛辣、露骨という意味でえげつないという言葉があります。
こんにちはという意味の挨拶としてごめんやすがあります。
トンチンカンや間抜け、見当はずれな人のことはすかたんと呼ばれます。
忙しいや落ち着かないという意味でせわしないやせわしいが使われます。
ぶっちゃけたこというとは今ではぶっちゃけとして若者言葉になってますが、元々は京都弁です。
ほっこりは疲れたや大変だったという意味であり、全国的な意味であるゆったりしたや和んだとは違います。
他にもたくさんの京都弁が存在しています。