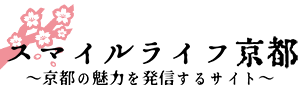京都の伝統行事(葵祭・ひな祭り他)

京都の伝統行事
京都は昔からの長い歴史のある土地のため、さまざまな伝統行事が現在存在しています。
そうした伝統行事には国内外から、数多くの観光客が集まり、京都の町は大変な賑わいを見せます。同時にそんな観光シーズンにはアルバイト募集も活発になり、京都近辺の人だけではなく全国規模での募集がされます。
京都府のリゾートバイト・求人情報です。京都には多くの魅力が詰まっており市街地はもちろんですが、それらを囲む山々にも独自の雰囲気があり京の街を語る上ではかかせない。中心地は、清水寺や金閣寺と言った歴史的建造物が多数集まっている他、ショッピングを楽しめる場所も多い、南部はショッピングや食文化の多彩な大阪府や歴史的建造物の多い奈良県にアクセスがしやすく、北部は丹波栗や黒豆といった名産品が多く雄大な自然を堪能できるエリア。
今回は京都の三大祭の1つである葵祭と下鴨神社で開催されるひな祭りなどに注目して紹介していきます。
京都の三大祭の1つ葵祭

葵祭(あおいまつり)は毎年5月15日になると上賀茂神社と下鴨神社で行われます。
京都の三大祭の1つで、三大祭の中でも最も古い歴史があります。ちなみに、三大祭といえば、葵祭の他にも祇園祭と時代祭があります。祇園祭は最も規模が大きいものであり、八坂神社が行っている祭りのことです。
京都に平安京がおかれる前から葵祭の行事は存在しており、約1400年もの昔から行われています。
農作物が被害を受けた時に、豊作を祈るために行われたのが最初だとされています。また、当時病気が流行っていたために、病気が取り除かれて一日でも早く健康な状態に戻ることを祈願して行われました。
平安時代においては祭りといえば葵祭のことを指していました。日本の祭りの中でもとても重要な位置を占めるものであり、他の祭りにもさまざまな影響を与えています。
お祭りの際には、京都御所から行列が出発して、下鴨神社を経由して、最終的には上賀茂神社へと向かいます。
平安時代の貴族の衣装を着た500人もの人達が牛車とともに歩いて行く姿は荘厳です。
かつての時代の雰囲気を感じさせるものであり、昔から変わらない姿で今でも行事が行われていることは感動できるでしょう。
一時期中断することもあったのですが、京都の住民たちの力によって現在まで続いています。
時代祭とは明治に企画されたものであり、各時代の風俗を表現するための時代行列が最初です。
下鴨神社のひな祭り「流し雛」

出典:お雛様を川に流してしまう?「雛流し(ひ なながし)」の意味と歴史 | 人形の東玉
3月3日といえば桃の節句 ひな祭りです。
そもそもひな祭りとは神事であり、人間が持っている穢れを雛に託して清めてもらうという意味があります。
それが現在ではひな壇にひな祭りを飾って祝う日となりました。
京都では、下鴨神社のひな祭りでは、雛人形を川に流すという行事が行われており、これを「流し雛」といいます。
これによって子供が無病息災で生きていけることを祈るという意味合いがあります。
神社では流し雛に参加するための雛人形が売られており、ひなあられもついてきます。
都踊り

京都には都踊りという伝統行事もあります。
こちらは1872年に始まったものであり、祇園甲部歌舞練場で開催される舞踏公演です。
源氏物語や歌舞伎を題材としており、今でも進化を続けています。
京都の行事に参加したい
他にも京都には色々な伝統行事が残されています。
それらの詳細はインターネットを使えば簡単に情報を得られます。
ある程度の規模の行事だけでもかなりたくさんあるため、1年ですべてに参加することは難しいかもしれません。
観光シーズンは非常に込み合うためリゾートバイトなどを利用して泊まり込みで働きながら地元の人のように京都の町を探索してみてはいかがでしょうか。