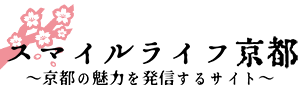京都府福祉のまちづくり条例

日本の現状
日本は少子高齢化が進展しており、これからますます高齢者の数が増えていきます。
高齢者の数が増えていて、若者の数が減っているため、高齢者を支える人の数は激減しているのです。
このままの状態が続くと、高齢者にとってはとても住みにくい町が生じてしまうでしょう。
このような少子高齢化は日本各地で進行しているものであり、京都も関係ありません。
そこで京都府では、京都府福祉のまちづくり条例を制定しており、これによってどのような方でも暮らしやすい福祉があるまちづくりに取り組んでいます。
この条例は高齢者や障害者であったとしても、誰でも快適な生活を送れるようなまちづくりを約束しています。
具体的にはたくさんの方が利用するような施設をバリアフリー化したり、お互いのことを尊重できるような多様な社会を作り出すことを目的としています。
互いに助けあって、どんな人でも辛い思いをしないような社会を目標としているのです。ノーマライゼーションを実現するための素晴らしい条例です。
地域社会の環境を整備することによって、特にお年寄りは大きな恩恵を得られるでしょう。
京都の福祉のまちづくりの具体例
京都にはたくさんの歴史的文化財があるのですが、これはできるだけ多くの方に共有しなければいけません。
文化財というのはすべての人間にとって平等に存在しているものだからです。
そのため、どのような方でも文化財を楽しめるように各施設のバリアフリー化が推進されています。
たとえば、社寺の中にはバリアフリー化が行われていないところがあります。
そもそもバリアフリーという概念が登場してから数十年しか経過していないから当然のことでしょう。
昔の建物の中にはお年寄りや障害者のことを無視しているものが少なくありません。
そこでたとえば西本願寺の通路を整備したり、車いすでも利用できるトイレを設置したりするのです。
もちろん、歴史的文化財についてはそれを保護することも重要なため、各施設において最適な整備方法を提案することも大切です。
文化財を保護することと、バリアフリー化を進めることを上手く両立させることが大切なのです。
京都をより開かれた街にするためにはバリアフリー化を推進したまちづくりは大事でしょう。
誰にでも暮らしやすく、過ごしやすい街であれば、またここに来たいと思わせることもできます。
スロープやリフトを設置したり、緩やかな階段を用意したり、点字付きの案内板を用意するなど工夫できる点はたくさんあるのです。
これらの整備は徐々に進められており、京都はバリアフリーが行き届いている場所として知られています。
どのような障害を持っている方であっても、快適にあちこち見て回ることができるのです。