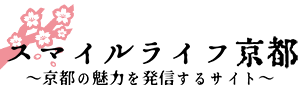京の怪

一条通りの百鬼夜行
京都といえば昔から妖怪がたくさんいることで有名です。
たとえば一条通では百鬼夜行を用いてまちおこしを行っています。
百鬼夜行というのは文字通り妖怪たちが夜に街の中を行進することです。
平安時代の京都においての出来事だとされており、当時の京都にはたくさんの妖怪がいたのです。
特に怪異が起きやすい日は夜行日とされており、この日の夜に外に出る際にはみんな魔除けの護符を持ち歩いていました。
本来、日本の鬼は人間の目に見えないものとされていたのですが、百鬼夜行は見えないはずのものが見えたとして言い伝えが残されているのです。
百鬼夜行に関して特に有名なものが百鬼夜行絵巻であり、それ以外にも多くの絵師が百鬼夜行に関する作品を発表しています。
百鬼夜行として付喪神の姿が多数描かれています。
付喪神というのは道具が変化した妖怪になったものです。
当時の日本にはアニミズムがあり、無生物にも魂が宿っているという考え方が一般的でした。
そのため、道具を大切にしないとやがて妖怪として化けて出てしまうと恐れられていたのです。
日本には道具を大切にするという文化がありますが、それは単に道具を大事にするべきという道徳的な考えが根付いていたのではなくて、付喪神を恐れた結果であるともいえるでしょう。
ただし、付喪神は恐れを抱かれていたのと同時に愛されていた存在でもあります。
だからこそ百鬼夜行絵巻のようなものが作られたのです。
一条通りは平安京の中でも北端に位置しており、当時の人達にとってここは外界との境界線として認識されていました。
そのため、ここで妖怪に出会ってしまうという話が生まれたのです。
京都魔界を楽しむ
京都は京都魔界と呼ばれることがあるほど妖怪に関する話がたくさん残されています。
たとえば祇園祭は疫神を鎮めるために行われたものであり、京都に遷都された原因というのは怨霊を恐れたためであるなど、京都には妖怪に関する話がつきものなのです。
中世の日本ではまだまだ妖怪の存在が信じられていたために、その時代の一番の都である京都には妖怪がたくさんいたのです。
ただし、江戸時代になると人々はそれほど妖怪を恐れなくなり、むしろ1つのキャラクターとして愛すべき存在として定着しました。
当時は読み物や絵などでたくさん妖怪が登場したのです。
現代になってもその傾向は続いており、多くの方が妖怪を愛しています。
京都を訪れる際にはかつてこの土地には妖怪がいたということを思い出しましょう。
少なくとも当時の人達の心の中には常に妖怪という存在が強い影響力を発揮していたのです。