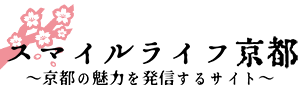歴史の町

誇りでもある
京都は長い歴史のある町といわれることが多いのですが、具体的にどんな歴史を経てきたのかきちんと理解している方は少ないでしょう。
京都の歴史の始まりは平安時代からです。
現在の京都のあるところに天皇が遷都して、そこに平安京ができたことから京都の長い歴史がスタートします。
それまでの都は数十年単位で場所が移されていたのですが、京都が都となってからは明治になるまでずっと日本の中心であり続けました。
千年近くも同じ都市が中心となり続けたのは世界的に見ても珍しいケースです。
そのため、今でも京都に住んでいる方は日本の都だったことについて誇りに思っています。
平安時代はその名の通り社会は比較的安定していて平和な時代が続きました。
そのために王朝文化が発展していった時代となります。
奈良時代はまだまだ中国の文化をそのまま取り入れている感じだったのが、平安時代になると日本独自の文化が花開きました。
遣唐使が廃止されて、国風文化が発展していったのです。
その結果として紫式部の源氏物語や清少納言の枕草子といった文学作品の数々が生まれました。
やがて武士階級が力をつけていき、京都は中世都市へと変化を遂げていきます。
鎌倉時代になっても京都の影響力はまだまだ力強くて、日本でも最大の都市として発展しました。
日本の経済的な中心地として君臨し続けたのです。
室町時代になると京都が政治的な中心地の座を取り戻すことができて、この時代に金閣寺や銀閣寺ができました。
応仁の乱が起きると京都は大打撃を受けるのですが、そこから乱が収まった後は復興を果たします。
その際に大きな役割を果たしたのが町衆であり、祇園祭も生まれました。
織田信長や豊臣秀吉の時代にも京都は重要な都市として認識されました。
江戸時代以降の京都
江戸幕府が樹立されたことによって、京都は政治の中心ではなくなりました。
しかし、文化や工業においては変わらず京都が日本の中心でした。
日本を代表する3つの都市の1つとして発展を続けたのです。
幕末になると欧米列強が日本に接触するようになり、その結果として幕府や天皇の存在がぐらつきました。
その結果として明治維新が起きて、最終的には新しい時代に変わりました。
当初は京都が首都に返り咲くと思われていたのですが、明治天皇が東京へ遷ってしまい、これによって京都は大打撃を受けました。
しかし、このような危機にあっても京都はさまざまな試みを実行して、都市として生まれ変わりました。
戦時中は幸いな事に空襲をほとんど受けなかったため貴重な文化財が残りました。
そのため、戦後は観光として発展して、今では人口が約150万人いて、日本を代表する都市としての地位を守っています。
京都にはこのような歴史があるのです。